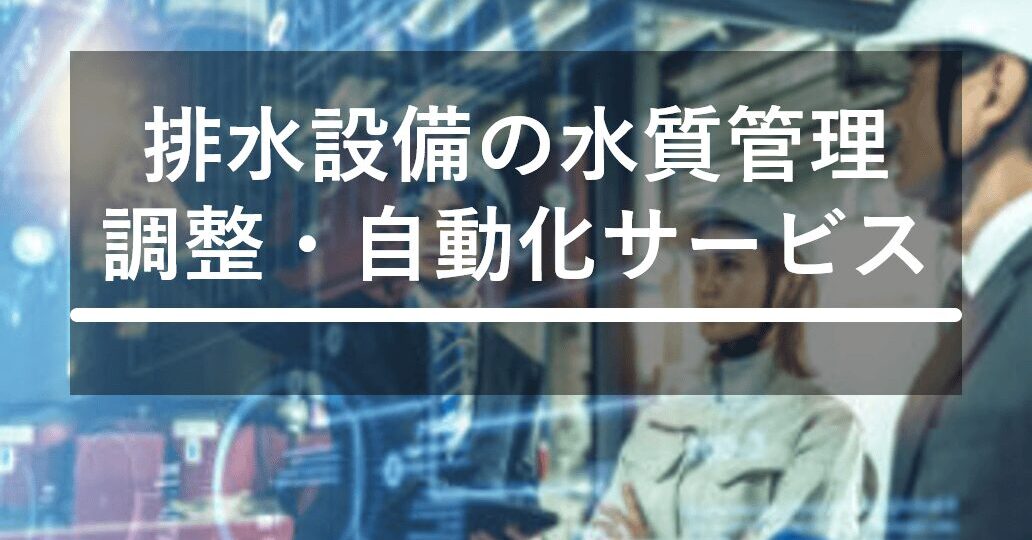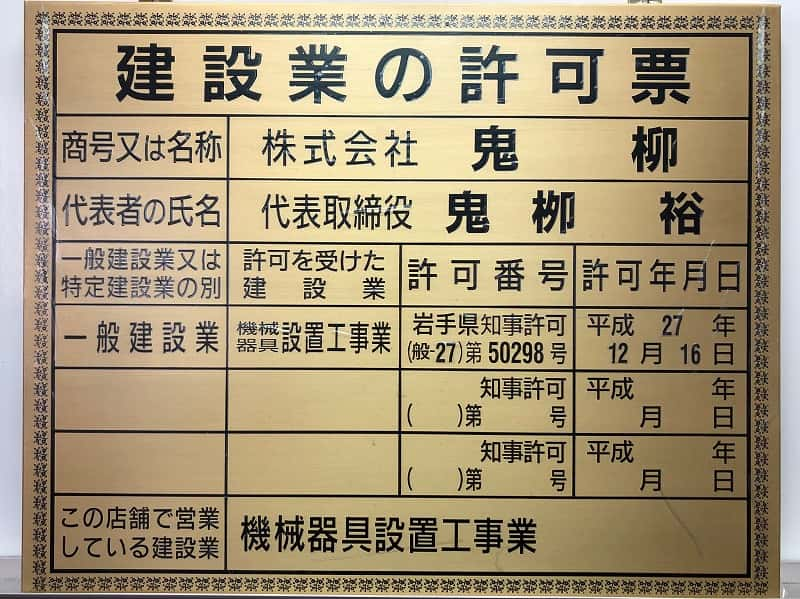このようなお困りごとはありませんか?
-

水質管理が属人化し、担当者の異動や退職で管理レベルの維持が困難に…
長年の経験を積んだベテラン担当者が培った「勘」や「コツ」に依存した水質管理では、その担当者が異動や退職した際に、同等の管理レベルを維持することが極めて困難になります。特にpH調整のタイミングや薬剤投入量の判断は、微妙な水質変化を読み取る経験値が重要となるため、新任者への技術継承には相当な時間を要します。また、引き継ぎ期間中は管理精度が不安定になりやすく、排水基準値の逸脱リスクが高まる恐れもあります。このような属人化を解消し、誰でも一定水準の管理ができる仕組みづくりが急務となっています。
-

人手不足で、日々の点検・記録業務の負担が増え続けている…
工場の排水処理では、1日に複数回のpH測定、薬剤投入量の調整、数値の記録など、多岐にわたる定期的な作業が発生します。人手不足が深刻化する中、これらの業務は担当者にとって大きな負担となり、本来注力すべき生産業務や改善活動への時間確保が困難になっています。さらに、手作業による測定や記録では、ヒューマンエラーのリスクも避けられません。測定値の読み取りミス、記録漏れ、薬剤投入量の間違いなどが発生すると、水質管理の信頼性に影響を与え、結果として監視体制の強化がさらなる工数増加を招く悪循環に陥りがちです。
-

排水基準の超過リスクと、それに伴うコストを抑えたい…
環境規制が年々厳格化する中、排水基準値の超過は企業にとって重大なリスクとなります。基準超過が発生した場合、行政への報告義務、改善計画の策定、場合によっては操業停止や罰金などの重いペナルティが課せられる可能性があります。また、基準値ギリギリでの管理を続けていると、わずかな水質変動でも超過してしまうリスクが常に付きまといます。一方で、過度に安全マージンを取った管理では、薬剤使用量の増加によるコスト上昇が避けられません。つまり、基準値を確実に守りながらも、無駄なコストをかけない最適な水質管理の実現が求められているのです。